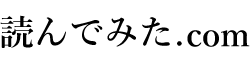城山三郎の『雄気堂々』です。
今年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』の主人公、渋沢栄一を描いた歴史小説。
令和6年に発行予定の新一万円札の肖像にも選ばれた実業家です。
渋沢栄一の名前を初めて知ったのは、三十年ぐらい前に読んだ荒俣宏の『帝都物語』だったと思います。
確か関東大震災後の帝都、東京を設計し復興させた人物として登場していたような…。
そんなわけで昔から、気にはなっていたのですが本屋さんで平積みになっているのを見て、つい、買ってしまいました。
渋沢栄一は天保11年(1840年)に武蔵国血洗島村(今の埼玉県深谷市血洗島)の農家の長男として生まれた。
生まれたのは藍染で使う藍玉の製造販売や養蚕を行う農家で村の名主(尾高家)に繋がる豊かな富農だった。
栄一は幼少の頃から親戚である尾高家の従兄に学問や剣術を習い、彼らの影響から尊王攘夷の思想に染まり倒幕活動を始める。
栄一と従兄の渋沢喜作らは、高崎城を落としその後、横浜を焼き討ちにし長州と一緒に幕府を倒そうと画策するが、尊敬する従兄の尾高長七郎に諫められ計画は頓挫。
栄一と喜作の二人は京都に逃げると、面識のあった一橋慶喜(後の徳川慶喜)の重臣、平岡円四郎に仕官、結局、慶喜の家来になってしまう。
その後、栄一は一橋家のために歩兵を徴用する仕事や一橋家の財政改革で功を成し出世を重ねていく。
栄一の悲願は慶喜が攘夷討幕のための軍を起こすことだったが、慶応2年(1866年)、皮肉にも慶喜自身が将軍になってしまう。
開国を意識していた慶喜は弟の徳川昭武を欧州に派遣。
その会計係として栄一も随行することになる。
二年の後、水戸藩主の急逝で藩を継ぐことになった昭武と共にパリから帰ると、すでに時代は明治。
栄一は慶喜が隠棲する静岡で慶喜に仕え、静岡藩の財政を支えるために株式会社のような事業を始める。
事業も順調に行こうかと思われたころ、栄一は大隈重信に請われて、できたばかりの明治政府の大蔵省で勤務することになる。
と、ここまでが、上巻で描かれていることである。
で、下巻はといえば。
大蔵省の中枢といったポジションで迎えられた栄一は大蔵次官の井上馨のもと租税制度など国の基本となる制度を整備していくが、いずれ薩長の藩閥の争いに巻き込まれていく。
そして税収を上回る予算を要求する司法卿の江藤新平らと対立した井上馨と栄一は官職を辞してしまう。
すると栄一は日本で最初の銀行、第一国立銀行(国立とはあるが民間銀行)の総監に就任。
時代は西郷と大久保の対立が激化、西南戦争がはじまり、その終焉を迎え、大久保も暗殺されてしまうといった頃。
その間、第一国立銀行に出資した小野組の倒産や養蚕業の振興、商工会議所の設立などに栄一は奔走する。
やがて、栄一は海運業を独占する三菱に対抗するため、出資を募り共同運輸会社を設立。
明治十五年、栄一が四十三歳の七月、妻の千代がコレラに罹って急逝。
物語はここで終わってしまう。
という訳で、九十一歳で亡くなった渋沢の実績を考えると四十三歳で完結というのは、かなり尻切れトンボといった感があります。
本作を読むと薩長側から見た幕末の歴史とは、また違う一面が見えてきます。
渋沢栄一はそもそも幕府側の敗者だったが、何となくという感じで勝者側になってしまうのですね。
そうした合理的な思考をもってはいるが、徳川慶喜を見捨てることもなく世話をしたりと義理堅いところもある。
そのあたりの性格が『論語と算盤』のような本を書かせるのでしょう。
また、家族や周囲の人たちとの出会いを考えると彼の運の良さというのも、ものすごく感じます。
タイトルとなっている『雄気堂々』とは栄一が好んだ「雄気堂々、斗牛(とぎゅう)を貫き、誓いて真節を将(もっ)て君の讐(あだ)に報ゆ」という中国、南宋時代に岳飛という武将が創った詩の一節からとったものです。
それにしても幕末から明治の初めに表舞台に立った人物の小説を読むと、いつも感じるのですが「戦後に生まれた我々に比べ、濃密な人生を送っているなぁ」と。
たかだか、10年や20年ぐらいの間に、とんでもなく多くの経験をしている。
それも本当に命を懸けたような経験を。
城山三郎の小説を読むのは久しぶりでしたが、読んでいて安心感があります。
ほんとは、渋沢栄一の晩年まで書きたかったのではないでしょうか?