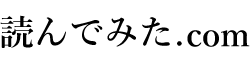ジェラルディン・ブルックスの『古書の来歴』です。
翻訳は森嶋マリ。
「いくつになっても、知らない世界を見たり聞いたりして新しい知識を得るというのはうれしいものだ」と思わせるような、そんな知的な興奮が沸き立つ小説である。
最初の数ページを読んで、これはアタリだと感じた。

本書は「サラエボハガター」といわれる、実在する14世紀のスペインで作られたハガターを巡る、いくつかの数奇な物語で綴られる。
ハガター(ハッガーダーともいわれる)とはユダヤ教の三大祭りの一つで春に行われる「過越の祭(すぎこしのまつり)」の際に読まれる祈りや詩などで編纂された冊子のことで出エジプト記を伝えるユダヤ教の聖典。
「サラエボハガター」は羊皮紙に手書きでヘブライ語の文章が書かれ、金や銀、ラピスラズリのブルー、サフランのイエローなど高価で貴重な顔料や染料で、細密で鮮やかな挿絵が多く描かれている。
当時、ユダヤ教では宗教画など偶像崇拝が禁止されていたと考えられていたが「サラエボハガター」が見つかったことで、そうした定説が覆ることになった。
「サラエボハガター」はボスニア博物館が所蔵していたが第二次世界大戦ではナチスに接収されそうになったり、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争では一時、所在が不明になる。
その後、発見されたが、この貴重なユダヤ教文書をイスラム教徒が守ったというエピソードが有名になったという。
このことを、モチーフとして描かれたのが本書である。
主人公はハンナ・ヒースという古書の鑑定の第一人者。
アラサーの独身女性で、しかも、オーストラリア人。
オージーの古書の鑑定家というだけで、すでに、予想を裏切られた感がある。
舞台は冬季オリンピックも開催されたこともある旧ユーゴスラヴィアの首都、サラエボ。
1996年、当時、サラエボはボスニア・ヘルツェゴビナ紛争末期の頃。
シドニーに住む主人公のハンナに所在不明だった「サラエボハガター」の鑑定を依頼する電話が舞い込む。
ハンナはサラエボに飛び、詳細な鑑定を行う。
物語はハンナが「サラエボハガター」の謎を鑑定の結果、見つかった手掛かりやサンプルを科学的に解析し、解き明かすかのように進んでいく。
それは第二次世界大戦当時のサラエボや、第一次世界大戦の足音が聞こえようとする頃のウィーン、17世紀初頭のベネチア、サラエボハガターが製作された15世紀のスペインとゆかりの地と時代を駆け巡る。
いずれもキリスト教の異端審問による焚書や紛争など多くの迫害を乗り越えて、現在、存在しているのは僥倖としか思えないような話ばかりである。
本書はフィクションなので、どのエピソードも作者の想像であり、事実とは異なるものなのでしょうが…。
「アンティークに歴史あり」という感じですなぁ。
また、本作が単に歴史教科書のような味もそっけもないものにならずに済んだのは、主人公とその母親の葛藤や、彼女の出自、そして、サラエボ国立博物館の主任学芸員とのロマンスなども上手に盛り込まれているからに他ならない。
このあたり、上手です。
作者のジェラルディン・ブルックスはオーストラリア出身の作家。
ジャーナリストとしても活躍し、小説の『マーチ家の父―もうひとつの若草物語』という作品ではピューリッツァー賞を受賞。
彼女の経歴を読むと、ハンナ・ヒースという主人公と似たものを感じるのは気のせいだろうか?
サラエボのある旧ユーゴスラビアは『七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家』といわれ歴史的にも政治的にも民族的にも宗教的にもメチャクチャ複雑である。
ユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった宗教と歴史。
そして、稀覯本に対する西洋の専門家たちの捉え方。
日本人には、あまり、なじみのない世界ではあるが、そしたことに、ちょっと目を向けてみようかと思わせるようなよい小説だった。
本書は2010年度の翻訳ミステリー大賞を受賞。
こういう、良書はもっと多くの人に読んでほしいものです…。