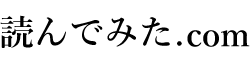恩田陸の『蜜蜂と遠雷』である。
結構なヴォリュームの作品だがぐいぐいと一気に読んでしまった。
こんなに、作品に引き込まれて読んでしまったのは久しぶりである。
場面への導き方が抜群に上手い。
こんなに上手いと著者自身の手のひらで踊らされている感がして自己嫌悪に陥る、そこがいやになる。
物語は吉ケ江国際ピアノコンクールという、おそらく「浜松国際ピアノコンクール」をモデルにしたのであろうというコンテストが舞台。
そのコンペティションに参加した、四名の若き演奏家の濃密な十数日間を描いたものである。
登場するのは天真爛漫で何を考えているのかよくわからない天才少年、過去の栄光から転落した音大の女子学生、スタイルも性格も演奏も完璧な外国人学生、奥さんと子供をもち楽器店で働きながらピアノに向かい合う青年。
ストーリーはシンプル。
それぞれが、様々な背景を持ちながらコンテストと対峙する。
これだけである。
正直、話ができすぎの感じはある。
きらきらした出来のよい少女漫画のような小説ともいえる。
少女漫画は、もう、何十年も読んだことがないが…。
「音楽は語れない」とはよくいわれることである。
音楽はいくら言葉を駆使しても100パーセント相手に伝えるというのは、どだい無理なのである。
音楽を相手に伝えるには、その音楽、それ自体を聴かせるしかない。
分かりやすくいうならベートーヴェンの交響曲第5番「運命」を、一度もきいたこともない人物に言葉で正確に伝えるのは不可能だ。
しかも聴かせられた「運命」ですら作ったベートーヴェンの音楽なのか、それを演奏したオーケストラの音楽なのかわからない。
もしかすると、それを鳴らした音響装置や聴き取った耳など自分の生理的なシステムが再生した音楽なのかもしれない。
あー、哲学でいうところのイデアみたいな話になってきた…。
閑話休題。
つまり、そうした言葉にできない音楽を著者は多彩な言葉を饒舌に繰りだし、力業といった感で読者を引き込んでいく。
こんな風に音楽を文字として紡げるのはすごい。
例えば作曲者や作品に対する膨大な比喩である。
このあたり、凄みを感じるし才能のある作家なんだと思わせる。
小説だからできることなのだと思うが、音楽に対する著者自身の定見といったものを持っていなければ、ここまではっきりと描くのは難しいだろう。
ある意味、楽曲に対する壮大な評論であり解説でもある。
音楽、中でもクラシックの世界を舞台にした小説は、スポーツを舞台にした物語、いわゆるスポコンと似ている。
登場人物の努力と栄光と挫折。
ライバルの出現。
最後に迎える大団円。
テーマは何であれ、このあたりのどこかに、人間を感動させる普遍的なサムシングがあるのだねぇ。
ちなみにクラシック音楽をモチーフにした小説なら藤谷治の『船に乗れ!』もオススメ。
本作は第156回直木三十五賞、第14回本屋大賞を受賞。
直木賞と本屋大賞の同時受賞は、本作が初めての快挙だという。
そんな訳で、恩田陸という多作な作家の名前は昔から知っていたが、今回、初めて読んでみた。
おススメ!