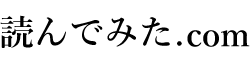須賀しのぶの『革命前夜』です。
当初は、恩田陸の『蜜蜂と遠雷』のような音楽だけが軸になる物語かと思ったのですが…。
違いました。
読み進めていくうちに音楽が大切な要素ではあるが、決してメインテーマになっているわけではないなと。
どちらかといえば、この物語の中心にあるのは壁の崩壊直前という特異な状況の東ドイツでの歴史に翻弄された若者たちのありようである。
当初、思っていたより、なかなか硬質。
第18回大藪春彦賞を受賞した作品だが、本格的なハードボイルドや冒険小説といった風でもない。
背表紙の本の説明に「歴史エンターテイメント」とあったが、自分としてはエンターテイメントという表現は少々、軽すぎるのでは? と違和感を感じる。
ジャーマン青春小説といった方がしっくりくるのではなかろうか? そうでもないか…
物語の舞台となるのは、壁の崩壊直前の旧東ドイツ。
主人公の眞山柊史(まやま しゅうじ)はピアノを学ぶ青年。
彼は1989年、昭和が終わった年に東ドイツのドレスデンに音楽留学する。
そこで、出会ったのはハンガリー人のラカトシュ・ヴェンツェルと東ドイツ人のイェンツ・シュトライヒという二人の才能豊かなヴァイオリニスト。
柊史は天才肌のヴェンツェルに見込まれ学内での演奏会の伴奏を務めるようになる。
一方で柊史はドレスデン旧宮廷教会でパイプオルガンを弾くクリスタ・テートゲスを見かけ、彼女の演奏に魅了されてしまう。
柊史はクリスタに思いを寄せるが、クリスタは国家保安省(シュタージ)の監視対象者だった。
同窓生の演奏家たちや彼が思いを寄せるクリスタといった若者たち、そして東ドイツで生活する人々との交流。
東ドイツの息苦しい監視社会で生活する登場人物たち。
柊史をはじめとする演奏家を目指す若者たちの思いや行動が、ベルリンの壁崩壊直前という特異な状況で交錯していく。
読み始めて、すぐに思ったのは「なぜ、東ドイツだったのだろう?」と。
主人公が音楽留学した1989年頃となると、若者に流行った東欧趣味みたいなものも終わっていたと思う。
フランスやオーストリア、西ドイツじゃ、ダメだったのだろうか?
クラシック音楽が中心に描かれているわけではないが、それでもクラシックのことにかなりの個所が費やされている。
音楽という得体の知れない奇々怪々ものを、迷いのない表現で描いてしまうこと、これはなかなかできないことだと思う。
恩田りくといい、なぜ、音楽という言葉にし難いテーマを軽々とアグレッシブに描けるんだろう。
読んでる途中、ずっと主人公に言いたいことがあった。
「あんた、そうしたことに関わっていたら偉大なピアニストになれないよ!」と。
蛇足ではあるが、『善き人のためのソナタ』というドイツ映画がある。
この映画を見てから本作を読むと、より理解が進むと思う。
映画自体、すごくいい映画だった。
おススメです。