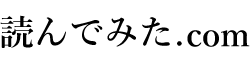浅田次郎の『終わらざる夏』です。
いやー、読ませます。
さすが、浅田次郎といった感じ。
舞台となったのはエトロフのさらに北、千島列島の最北端にある占守島(しゅむしゅとう)。
本作を読んで初めて、その存在を知りました。
先の敗戦までは、こんな北の果てまで日本の領土だったのですねぇー。
昭和20年6月、大本営の編制科動員班は敗戦の処理を視野に最前線の部隊に英語が達者な兵員を配置するよう決定する。
7月、東京の神保町にある翻訳専門の出版社に勤務する片岡直哉は、岩手県の実家に召集令状が届いたという報せを聞く。
兵役年限の四十六歳を、あとひと月もすれば迎えようとする片岡にとって、それは思いもかけないことだった。
片岡には女子高等師範(現お茶の水女子大)を卒業後、出産まで編集者として働いた妻の久子と信州に疎開している4年生の息子の譲(じょー)がいた。
そして、一家の住まいは世間も羨む文京区の同潤会アパート。
岩手県の田舎から上京し東京外語学校を卒業した片岡は、いうなれば当時の勝ち組といった生活を送っていた。
召集令状に従い片岡は配属となる弘前の聯隊に向かう。
家族はバラバラになり戦争という状況下、新しい境遇でそれぞれの生活を送ることになる。
片岡が配属になる弘前の聯隊に向かう途中、一緒になったのは同郷の軍曹の富永熊男と医学生の菊池忠彦。
富永は、3度の応召を経験し満州事変で勲章を授与された古参の輜重兵(武器や食料などの輸送する車両を担当する兵士)。
部隊でも我が物顔で振舞うが、輝かしい軍歴のために上官も咎めることができない。
一方、医学生の菊池は岩手医専卒で帝大医学部の学生。
岩手医専では徴兵された者の家庭の事情を斟酌し、徴兵されないように適当な病名をつけていたという若者。
このデコボコトリオが配属された占守島には関東軍の精鋭戦車部隊が無傷で配備されていた。
それは米軍が上陸する想定で配備されたのだが、輸送艦の不足により本土決戦のための配置換えもままならないありさまだった。
また、この島には食糧確保のため日魯漁業の缶詰工場があり、400名の女子挺身隊を含む2500人の民間人が送り込まれていた。
玉音放送があった八月十五日の三日後の八月十八日、ソ連軍が占守島に上陸。
日本軍はソ連軍と応戦する一方、日魯漁業の責任者は400名の女子挺身隊の娘たちを北海道に脱出させるべく行動を起こすのだった。
といったようなことが、多くの登場人の生き様やエピソードで紡がれていく。
この作品には積極的に戦争に関わっていく人物は描かれていない。
いずれも、戦争に巻き込まれてしまった人間ばかりだ。
本作はフィクションの部分が多く、あくまでも史実をベースにしたと小説ととらえるのがよいのだろう。
終盤については、主人公である片岡をもう少し丁寧に描いてほしかった。
他の登場人物とエピソードに埋もれてしまったような気がする。
また、ロシア人の兵士が登場するファンタジーのようなくだりはない方がよかったように思う。
浅田次郎らしいといえば、らしいのだが、このあたりに策士、策に溺れるといった風を感じる。
それでも、やはり上手いと思うし、読みごたえもある。
なにより、戦争という悲劇を改めて考えさせられる作品であるのは間違いない
本作を読んでいる間、フィリピンで戦死した二人の伯父のことがずっと頭にあった。
写真でしか見たことのない人たちだが…。
いったい、どんな人物たちだったのだろうか?
そんな思いが、より強くなってきた。