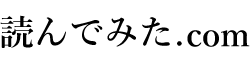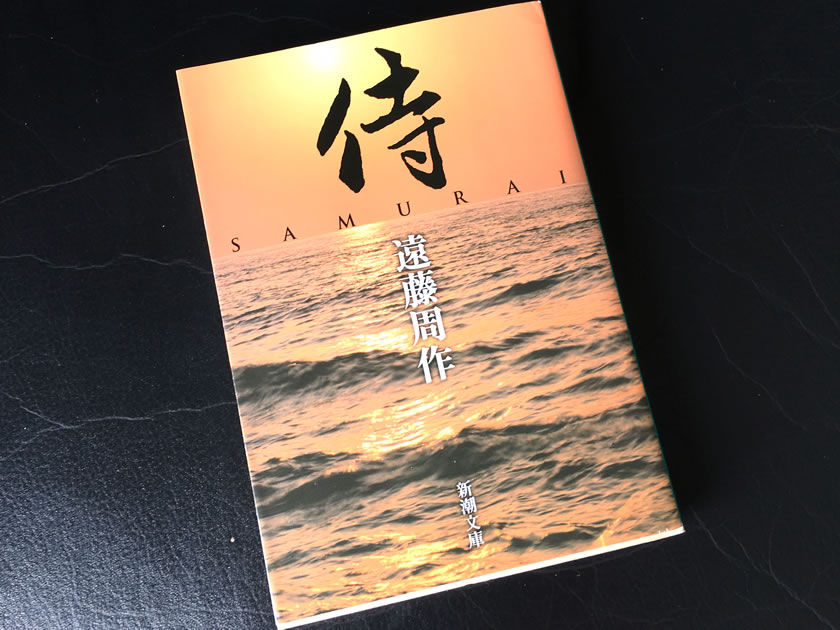
遠藤周作の『侍』である。
野間文芸賞受賞作。
何とも、鬱々とした小説である。
先日、マーチン・スコセッシが監督した『沈黙』という遠藤周作が原作の映画を観た。
禁教令が敷かれた当時のキリシタンや宣教師の過酷な人生を描いたもので、奉行を演じたイッセー尾形がいい味を出していた。
そんなこともあり「そういえば、遠藤周作のちゃんとした小説って読んだことなかったなぁ」と思い、手に取ってみた。
思えば高校生の頃、狐狸庵先生のエッセーはずいぶん読んだ。
今の若い人は狐狸庵先生なんていっても、遠藤周作のことだとピンとはこないだろうなぁ。
遠藤の作品自体、あまり読まれない時代だとは思うが…。
さて、本作である。
時代は関ケ原の戦いが終わり、豊臣から徳川へと時代が大きく舵を切ろうとしている頃。
家康により、これから、キリスト教が禁教とされキリシタンが迫害されようという時期である。
東北の寂れた土地で暮らす下級武士の長谷倉六右衛門。
彼は藩主の命により突如、ノベスパニア(現在のメキシコ)との交易を求めて、イスパニア(スペイン)国王とローマ法王への使節団の使者を命ぜられる。
日本での布教を条件に、使節団の案内役を務めるのはポーロ会の宣教師のベラスコ。
商人なども含む使節一行は藩が建造したガレオン船、サン・フアン・バプティスタ号で、太平洋を横断しメキシコに渡る。
そしてメキシコからサンタ・ベロニカ号に乗船し大西洋を横断し、日本を出てから1年半の時をかけスペインに渡る。
藩主の命を成就させるために、カタチだけキリスト教に帰依し、なんとかバチカンで法王と謁見し、苦労の末、帰国すると待ち受けていたのは、あまりにも理不尽な仕打ちだった。
作者の視点は、偉業ともいえる日本人が初めて太平洋から大西洋を横断したという冒険には向かっていない。
運命を苛烈なほどの意識をもって自分で切り開こうとするベラスコ、一方、自分の意思がいかようであろうと運命に抗うことなく身を任せる六右衛門。
この対照的な二人を浮き立たせることによって、日本人の持つ無常観がいかにキリスト教と相性がよくないかを説くことが本書の底流にはあるのでなかろうか?
宣教師ベラスコのキャラクターに寄るところも大きいと思うが、キリスト教的な暑苦しさがなんとも居心地悪い。
日本への布教をめぐりポーロ会と反目するペテロ会のヴァレンテ神父は、日本の布教を続けるかあきらめるかという司教会議の際、次のようにいう
日本人は本質的に、人間を超えた絶対的なもの、自然を超えた存在、我々が超自然と読んでいるものに対する感覚がないからです。…。この世のはかなさを彼らに教えることは容易しかった。もともと彼らにはその感覚があったからです。だが、怖ろしいことに日本人たちはこの世のはかなささを楽しみ享受する能力もあわせ持っているのです。その能力があまりに深いゆえに彼らはそこにとどまることの方を楽しみ、その感情から多くの詩を作っております。だが日本人はそこから決して飛躍しようとはしない。飛躍してさらに絶対的なものを求めようとも思わない。彼らは人間と神とを区分けする明確な境界が嫌いなのです。…。
主人公のモデルとなったのは伊達藩の下級武士、支倉常長。
彼は伊達政宗の命を受け慶長遣欧使節団を率い太平洋・大西洋を往復し、スペイン国王のフェリペ3世やローマ教皇パウルス5世と謁見し帰国した。
読み終えて「ああ、昔の作家というのはこういう感じだったなぁ」としみじみ思った。
風格を感じる文章には浮ついたところがない。
地に足の着いた小説という感じがする。
著者自身カトリックの洗礼を受けたクリスチャンであるが、彼のキリスト教に対するアンビバレンツな宗教観が本作にはあるのでないだろうか?