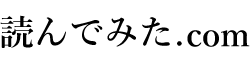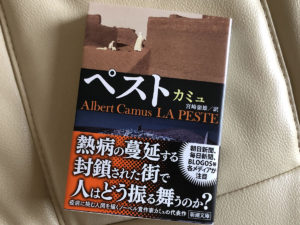高田大介の『まほり』です。
民俗学をモチーフとしたアカデミックな香りがする伝奇小説。
以前、新聞の書評で取り上げられていて「読んでみたいなぁ」と…。
その記憶が頭の片隅にあり、行きつけの図書館で見つけたときはラッキーといった感じで、さっそく借りました。
読み始めようとしたところで、タイトルの「まほり」とは、いったいなんぞや? と…。
電子辞書の「精選版日本国語大辞典」を引くも載っていない。
この疑問が終盤に本作のカギとして現れます。
主人公の勝山裕は社会学を専攻し大学院へ進もうと考える大学四年生。
彼のもとへ同窓の学生たちから都市伝説をテーマにしたゼミの卒研グループ研究を手伝ってほしいと頼まれる。
そして、飲み会の席で女学生から聞いた説話に裕はひどく惹きつけられるのだった。
それは裕の出身地である群馬県のある町であった出来事で、二重丸を描いたお札が町のあちらこちらに張られているという現象だった。
そのことを見つけた地元の子どもたちは、お札の謎を調べようと町中を探索するうちに近くの山中にあるお堂まで導かれ、その中に眼帯をしたような子どもを発見する。
果たして、それは本当に子どもだったのか?
裕は二重丸の謎を解明しようと地元に戻ると図書館で働いていた昔なじみの香織と偶然出会い、一緒にフィールドワークを開始する。
一方、地元に住む中学生の淳は、ひとりで山中で見かけた謎の少女を探していた。
裕達と淳は各々、異なる方向からアプローチを始めるが、そこから明らかになってきたのは、古くから地元に伝わる不思議かつ残酷な因習だった。
あらすじは、ざっくり言えばこんな感じですが、ディテールはかなり緻密。
江戸期における飢饉や間引き(子殺し)などについては多くのページが割いてあり、なかなか勉強になる。
言語学者という肩書を持つ作者が書いた小説らしく、資料としての古文書をそれらしく登場させ、それを解読するプロセスなども、かなりリアルかつ具体的。
また、主人公が助けを求めた歴史民俗博物館の朝倉や郷土資料館の古賀とのやり取りが面白い。
このあたりに、著者の学問のための記録に対する考えがすごく顕れている。
例えば古賀は裕に次のように言って諭す。
…真実性がある程度保証されているような勝れて客観性を認めうる資料であってすら、それが書き残され、保存されてきたということには、それだけで特別な意味が生じるということです。虚実を言えば、そもそも資料が存在するというまさにそのことに既に虚実が孕まれている。純粋に客観的であるような史料など原理的にありえないということです。史料の存在自体がすでに書いたものの底意、保存したものの意志の働きを帯びているということです。そしてそれを出来うる限り客観的な形で今日に読み解き、将来に向けて紹介伝承していこうとする我々史学者の営みもまた、同じくなんらかの底意、なんらかの意志の働きを免れえないということなんですよ。史学そのものが、透明なものではありえない、史学こそが、何らかの歴史、何らかの事実というご大層なものが形作られ、維持されていくのに手を貸してしまわざるを得ないという、この背理に自覚的でなければならない理屈でしょ。歴史学は廉潔であろうとすればするだけ、客観性という幻想に対して慎重であらねばならない。
こんな風に社会学や民俗学、歴史学に関する著者ならではの含蓄や向き合い方がいろいろと開陳されている。
惜しむらくは、小説としての構成と文章がもう一つ熟れていない印象を持った。
坂東眞砂子が亡くなって以降、現代を舞台に民俗学を中心に据えた伝奇(ホラー?)小説の書き手が、あまりいないような気がする。
昔は五木寛之も、結構、書いていたのに…。
こうした分野は個人的に好きなので、次作も期待したい。
一つ付け加えると主人公の母親の秘密は物語の途中で予想はできたが、最後の種明かしの方法がよかった。