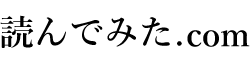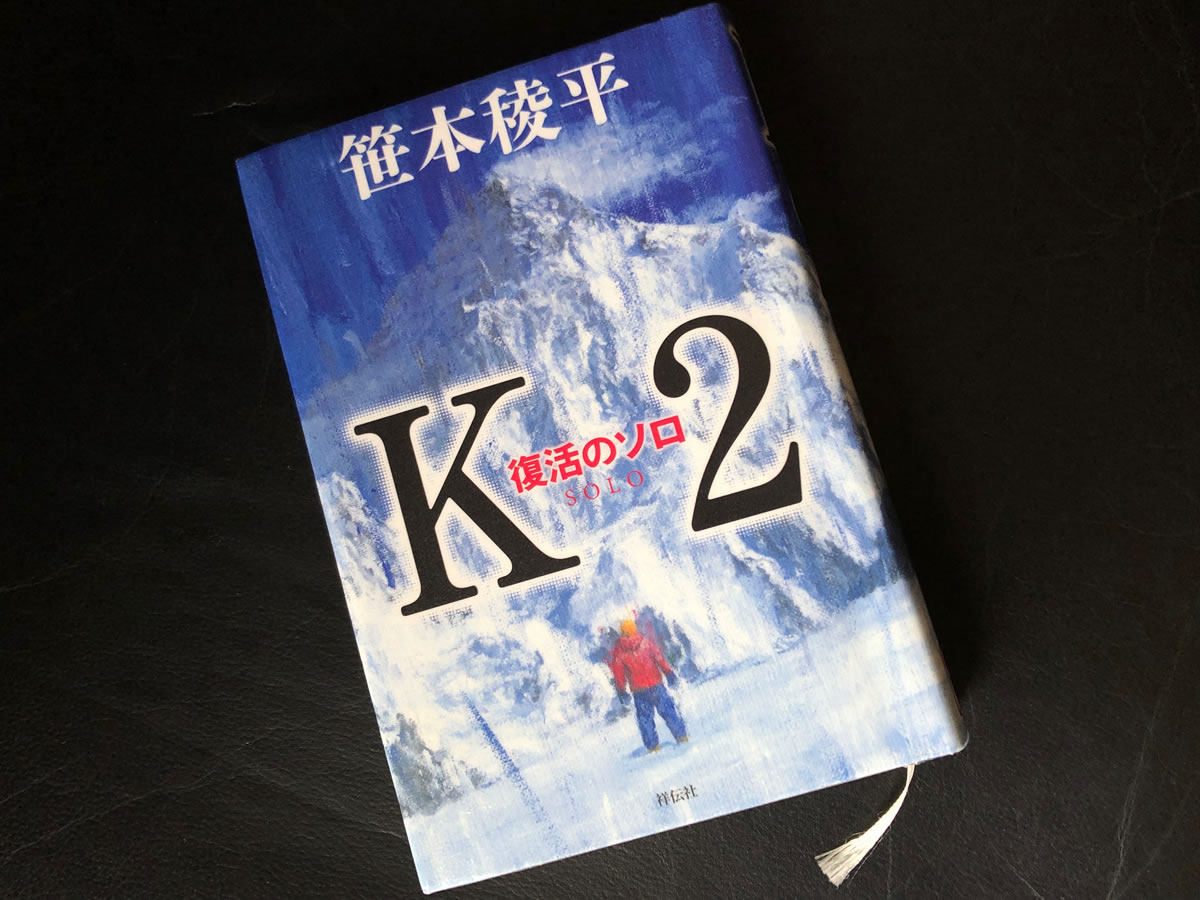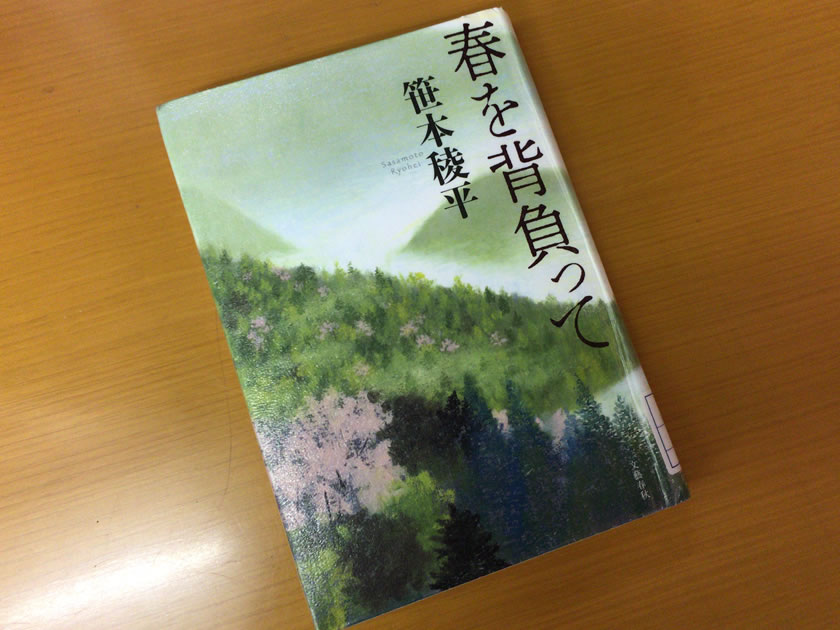笹本稜平の『大岩壁』である。
著者、お得意の山岳小説。
骨太の山岳小説といっていい。
それなりに読みごたえはあるし、面白いことは間違いない。
ただ、なんとなく素直に、いい山岳小説だといえない気分がある。
舞台となるのはパキスタンにある、標高8,125メートルのナンガ・パルバット。
ウルドゥー語で「裸の山」を意味する山の名前は、富士山と同じように周囲に連なる高い山のない独立峰であるところから由来する。
標高こそ世界第9位だが、その気象は独立峰であるがため苛烈を極める。
初登頂は1953年7月。
ドイツ隊とドイツ・オーストリア隊の6度の挑戦を退け、7度目の挑戦でようやく初登頂にこぎつけた。
その間、実に31人もの命をうばっている。
そのため、通称「魔の山」とか「人食い山」ともいわれている。
余談だが、世界で一番多くの遭難死亡事故を起こしているのは谷川岳で、やはり、「魔の山」とか「人食い山」と呼ばれている。
主人公の立原祐二と木塚隆、倉本俊樹の3人のパーティはナンガ・パルパットの冬季初登頂に挑戦するが標高7500メートルの岩壁で猛烈な嵐に襲われ撤退を余儀なくされる。
その下山途中、倉本俊樹は本人の高所障害に起因する事故のために亡くなってしまう。
そして5年後、立原祐二とパートナーの木塚はリベンジを図ろうと再度、冬のナンガ・パルパット初登頂を目指す。
そこに現れた一人の大学生クライマー倉本晴彦。
彼は亡くなった倉本俊樹の弟のだった…。
兄に対する特別な思いを抱いた晴彦を加えた、3人のパーティーは再度、冬季のナンガに挑むのだった。
昔の、例えば新田次郎の時代の山岳小説というのは、主人公の山に登るという行為への向き合い方や行動、心理状態描くだけで物語になった。
登頂が困難な山なら、なおさら、そうした傾向は強い。
しかし、最近はそれにプラスしたサムシングが必要になってきているような気がする。
いうなれば、山岳小説もノーマルルートだけでなく、バリエーションルートを登らないと読者に満足を得てもらえないような時代になってきたのではないだろうか?
本書も物語自体は、異物としての晴彦が混入しなければ普通の山岳小説として終わったかもしれない。
そのあたり、自分は、もっと、普通の山岳小説にしてもよかったのではないかなと思ってしまったわけです。
と書いたはいいが、様々な実録などを読むと登攀が困難な山を登るパーティーにおける人間関係のトラブルは決して珍しいことではない。
生存すること自体が困難な極限の場所における人間というのは、むき出しの人間性というものが現れる。
自分のことだけでいっぱいいっぱいで、情けをかけて仲間のことを気遣えば、最悪、自分自身も死んでしまう。
例え、十分な準備をしたとしたとしても、世話をするほうか世話になるほうか、どちらの立場になるかは、ある意味、登ってみないと分からない。
このあたりが山岳小説の醍醐味なんだと思う。
それにしても倉本の家族というか、ことに母親は可哀そうだ。
ちなみにナンガ・パルバットの冬季初登頂はイタリアのモーネ・モロら3名によって2016年2月26日に成功した。