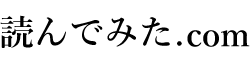吉田修一の『パーク・ライフ』です。
ずいぶん昔に買ってそのまま、積読になっていた。
風呂に入って読むのに手ごろなものが見当たらなかったので、たまたま視界に入った文庫本を「薄いし短編だし、いいかな」と思い風呂場に持ち込む。
この文庫本には「パーク・ライフ」と「flowers」の二編が収められている。
湯舟に浸って、読み進めてからビックリ。
「これって、純文学だったのか…」と。
読むまでは直木賞的な、軽妙な青春小説かと思っていた。
「パーク・ライフ」は有楽町駅と東京駅の西側にある日比谷公園を舞台にしたストーリーがあるようでないような小説だ。
主人公はバスソープや香水を扱う会社で広報兼営業をやっている若いサラリーマン。
彼は地下鉄の日比谷線で偶然であった女が、いつも昼休みに訪れる日比谷公園の常連だったと知る…。
日比谷公園の景色を記憶の片隅から手繰り寄せるように思い出しながら読み進める。
読みながら「そういえば、純文学ってこういうもんだったなぁ」などと思ったりする。
それほど沢山の吉田修一を読んだわけではないが、彼の作品を読むと「どこか、淡々としていて乾いている印象」がつきまとう。
終盤の公園で知り合った彼女が「よし。・・・私ね、決めた」と呟いて、別れるシーンは、読んでいて、なぜか梶井基次郎の檸檬とオーバーラップした。
一方の「flowers」は谷崎潤一郎かと、ちょっと思ったがやっぱり梶井基二郎だった。
序盤は怪しくて、エロいけど、文章が乾いているので湿った感じがない。
終盤、主人公がシャワールームで先輩と暴力沙汰を起こすシーンの文章は圧巻。
すごく文学的だし、作者のテクニックを感じさせる。
両方の短編を比べると、描いている内容の振り幅は大きいが、筆致が変わらないせいか違和感なくスッと読める。
パーク・ライフが芥川賞を受賞したのは読み終わってから知ったことだが、自分としては『flowers』のほうが芥川賞的な印象を受けた。