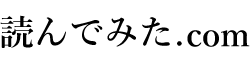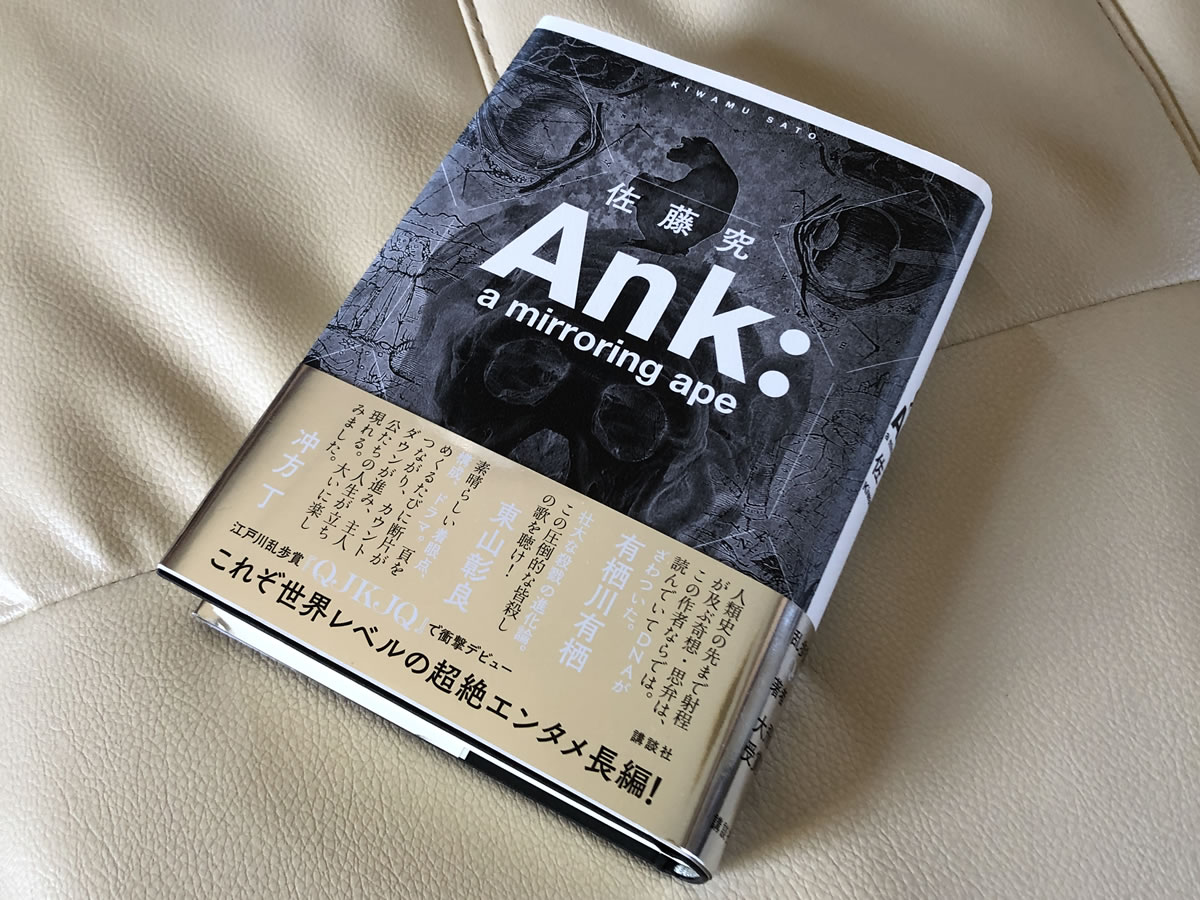
佐藤究(きわむ)の『Ank: a mirroring ape(アンク: ア・ミラーリング・エイプ)』です。
やー、スゴイ。
なんか、今どきといった感じの小説ですね。
最初は今どきのSF小説特有のとっつきにくさを感じた。
わかる人だけわかってくれればイイ的な。
また、物語を構成するセクションが細かく、各セクションの時間軸が前後したり、異なる人物の視点で描かれたりという手法が多用されていることも、とっつきにくさを感じる原因になったかもしれない。
しかし、読み進めるうちに、だんだんページを手繰る手が止まらなくなった。
2026年、秋、京都で暴動が発生するところから物語は始まる。
主人公の鈴木望は京都大学霊長類研究所の出身の研究者。
望は自分の論文がAIテクノロジーで財を成したシンガポールの億万長者ダニエル・キュイの目に止まったことを機に、世界で最高レベルの霊長類研究センター(KMWP)のセンター長をまかされることになる。
あるとき、その研究所にアフリカから怪我をした一匹のチンパンジーが運び込まれる。
アンクと名付けられたそのチンパンジーは驚異的な知的能力を見せ始める。
そして、アンクには人々を暴動に導く何かがあった…。
物語は、さも事実であるかのような情報が積み上げられてできている。
舞台が京都というのはよい場所に目をつけたと思った。
京都には京都大学霊長類研究所と言う世界的な権威がある。
遺伝子のサブターミナルサテライト反復(StSat:チンパンジーやゴリラなどの類人猿には染色体のテロメアとサブテロメアの間にあるが、ヒトにはない)とか小道具の使い方がいやらしい。
StSat反復があるゴリラ、チンパンジー、ボノボと、それがないオラウータンの間には自己鏡像認識(鏡を見たときに自己を認識する能力)の能力に差があるといったような論が語られ、これって、本当なのというような事実や作者の考えがまぜこぜになっていて、妙に説得力がある。
人々が暴動に導かれる原因となったアイディアは昔からあったが、その、切り口が斬新。
と、ここまで書いてふと思った。
アンクというチンパンジーがアフリカから京都の研究所まで連れてこられるまで何事もなかったのだろうか?
アンクには相当なストレスが、かかるような状況があったと思うが…。
本作は第20回大藪春彦賞及び第39回吉川英治文学新人賞を受賞した。
ちなみに、自分は車を運転するときにハードロックを聴くと人格が変わります。(安全運転の範囲で)