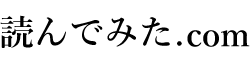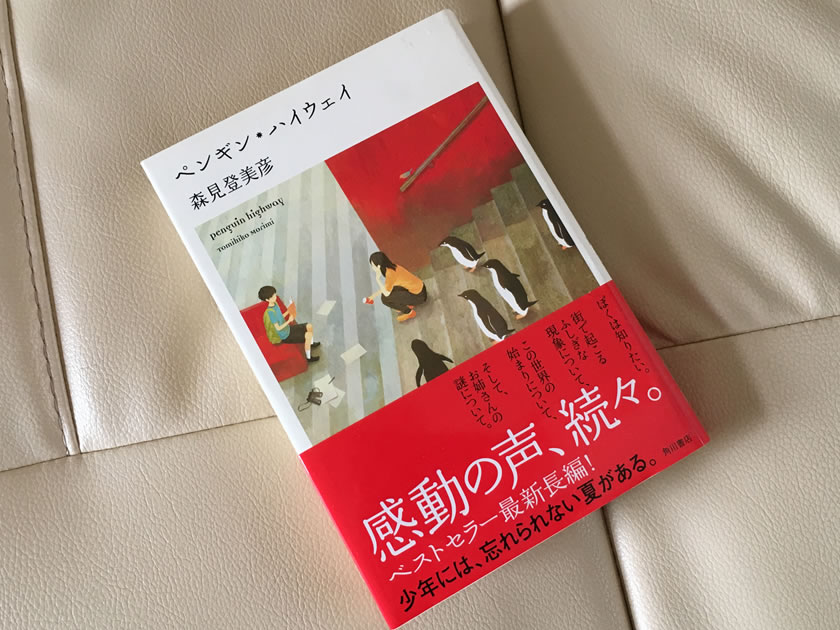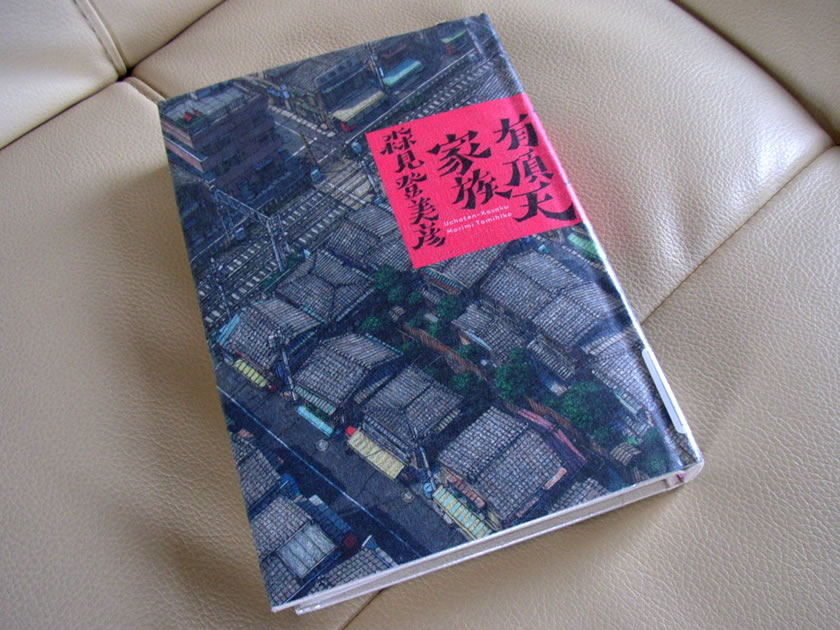森見登美彦の『熱帯』です。
いやー、これは、なんというか、どう言っていいものか…。
そんな風にしかいえない壮大な怪作(著者自身も本の帯に書いていた)であり、本や読書を愛する種族にとっては類まれにみる傑作ではないかとも思う。
とはいえ、誰にでも推せる作品ではないし、よくわかんないという人や、イマイチ推せないという読者がいても全然、不思議ではない。
本作のマジックリアリズム的な部分がそうさせるのか、読んでいるうちに南米のノーベル文学賞作家、ガルシア=マルケスの作品が頭をよぎった。
文章が平易でポップなのでマルケスほど、大げさな感じはないが、物語としてのスケールの大きさは『百年の孤独』や『族長の秋』にも匹敵するのではないだろうか。

物語のあらすじを簡単にいうならば、というほど簡単ではないないのだが、ゴリゴリと力ずくでいうならば、佐山尚一なる人物が書いた『熱帯』という、誰も結末を知らないといわれる小説を巡る冒険譚? である。
といってはみたものの、話はなかなか込み入っている。
鏡の姿見に映る鏡を持った自分を見るような感じとでもいうのだろうか物語が幾重にも入れ子になっているのだ。
でなければ、メビウスの輪かクラインの壺のような作品といってもいい。
物語を通じて重要な役割を演じているのが「シンドバッドの冒険」や「アラジンのランプ」で有名な『千一夜物語』。
読み始めは、モリミーといわれる著者独特の節回し全開の軽い文章で、スラスラとストーリーが頭に入ってくる。
本作の著者自身であろうモリミンといわれる小説家の生態が描かれたり、神保町のランチョンという実在するレストランが登場したりと現実感たっぷりのリアルな物語だったはずなのだ。
最初のチャプターあたりでは、フンフンと鼻歌交じりで読めるような気楽さがあったのだが…。
だんだん「いや、待て待て」といった具合になっていくのである。
「不可視の群島」という作品中盤のチャプターあたりから物語はコンフュージョンしていく。
主人公も白石さんという若い女性から、池内という中年男性、モネと呼ばれる男、そして、「熱帯」の著者、佐山へとメタモルフォーゼしていく。
後半になると、「ふと気が付くと」というセンテンスで場面転換することが多くなり、ちょっと、雑かなと思ったりもする。
そんなわけで「これはメモを取りながら読まないと、物語の全体像をとらえられなくなりそうだ」と思い、実際、ページの初めに戻ってメモを取りながら読み終えた。
ブログとか書かなければ、そんな、作業も必要なかったと思えるが、これをネタに一本書こうという自分にとっては、なかなか骨の折れる読書だった。
ところで、背表紙に書かれた座標のような英数字には何か謎があるのではないだろうか?