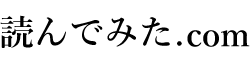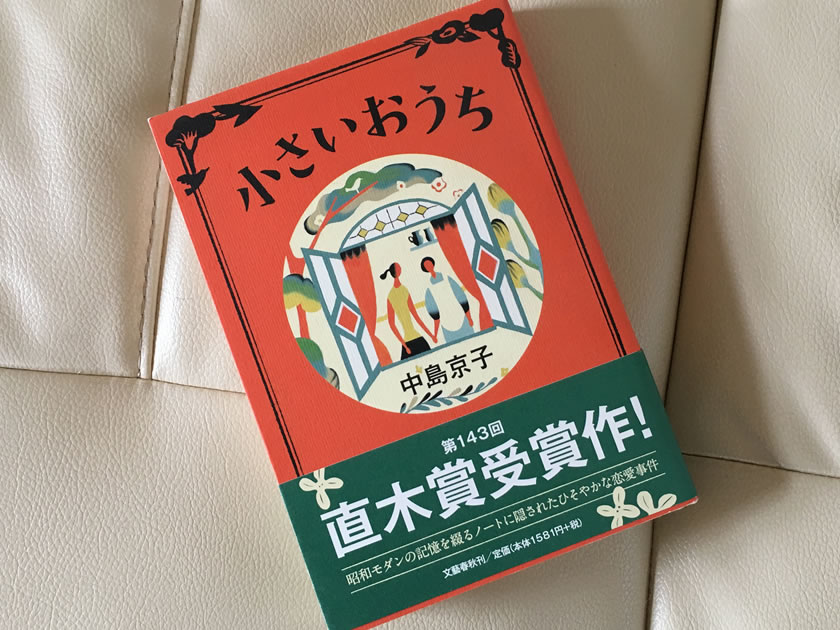中島京子の『夢見る帝国図書館』である。
本読みといわれる種族にとっては、なんとも愛おしい小説だ。
中心に据えられているのは東京の上野に日本で最初に造られた国立図書館である帝国図書館。
昔は通称「上野図書館」と呼ばれていたが、現在は「国立国会図書館国際子ども図書館」と名前を変え児童書専門の図書館になっている。
物語は主人公である“わたし”が小説家になる以前、ライター時代に上野公園で風変わりなオバサンの喜和子さんと知り合うところから始まる。
主人公が小説家ということもあり「モデルは著者、本人なのかな?」なんて、思いながら読み進める。
喜和子さんから、“わたし”は上野図書館を主人公にしたような「夢見る帝国図書館」というタイトルの小説を書くように勧められる。
しかし、“わたし”は、それは、喜和子さんが書くべきだと突っぱねる。
中島みゆきの『糸』ではないが、“わたし”と喜和子さんとの関係が縦糸に、帝国図書館の成り立ちから戦後までの歴史が横糸に物語は織りなされていく。
そして、そのほかに喜和子さんが書いた、戦後、彼女が上野で孤児だったときのことを描いた物語の一片も挿入される。
構成が、なかなか、凝っているのだ。
歴史上の文豪たちもたくさん登場する。
例えば帝国図書館が開設されて間もないころ永井荷風の父の久一郎がエピソードに始まり、樋口一葉や宮沢賢治、幸田露伴と淡島寒月、谷崎潤一郎、芥川龍之介、etc。
そして、戦後に現在の日本国憲法の制定にかかわるベアテ・シロタの活躍、他にも本の分類法である日本十進法についての逸話など歴史の一端を知ることができる。
太平洋戦争前後を描いたところなどを読むと、著者が直木賞を受賞した『小さいおうち』が思い起される。
上野動物園の象の花子のこと(有名な話だが)、日本陸軍が侵攻した香港で図書を略奪したこと、東京が空襲にさらされ戦局が厳しくなり蔵書が疎開されたことなど、描かれているエピソードの一つひとつが興味深い。
ちょっと、残念なのはキャラの立った喜和子さんには最後まではつらつと元気に登場していてほしかったことでしょうか。
まぁ、そうなると物語の展開も相当、変わったものにはなったでしょうが…。
三十年も昔、東京に住んでいたころは、もっぱら通学や通勤する圏内ばかりをウロウロし生活に関係のない場所はほとんど行かなかった。
今にして思えば、「もったいないことをした」と後悔しきりである。
本書の舞台となる上野近辺や根岸、谷中あたりを、ぶらぶらしておけばよかったなと…。
なんか、あのあたりは明治の文人の香りがする。
登場する湯島聖堂は行ったことがあるが、行っただけみたいなものでほとんど記憶はない。
安定のリーダビリティの高い柔らかな文章で、残業を終えて疲れた頭でも、ノープロブレムといった感じ。
読みやすくスラスラと頭に入ってくる。
おススメです!