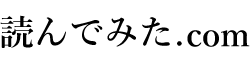司馬遼太郎の『世に棲む日日』である。
吉田松陰と高杉晋作の生き方を描いた小説。
司馬遼太郎のエッセイを読んでかねてから心に残る言葉があった。
「吉田松陰の母親のお滝は自分の孫に『松蔭叔父のようにおなり』とつねにいいくらした」というくだりである。
吉田松陰は幕末にアメリカに密航しようとした罪で獄死した人物。
そうした人物にもかかわらず、母親は「松蔭おじのようにおなり」と孫たちに語って聞かせる。
母親にそんな風に言われ、自分を祀る神社まで建立されてしまう人物というのはどんな人間なのだろう。
読み進むにつれ主人公は吉田松陰から高杉晋作に変わっていく。
2巻目の半ばまでが主に松陰について語られ、のこりが高杉のことについて綴られている。
山口県の方々には怒られそうだが、松蔭については稀代のパフォーマーというかイイカッコしぃだと思った。
あまりにも純粋すぎて幼さなすぎる。
よくいうなら、真っすぐすぎる。
これでは、周囲の友人や家族はずいぶん迷惑だろう。
個人的には松陰よりも高杉晋作に共感を覚える。
たぶんに著者自身が松蔭よりも高杉のほうに思い入れが深く、そのことが作品の中に映されていたせいもあるかもしれない。
高杉晋作についてはその名前は知っていたが具体的に何をやった人なのかほとんど知ることがなかった。
自分の中で坂本竜馬や西郷隆盛に比べ、高杉の存在感が薄いのは彼の活動自体が長州という地域に限定されていたせいと29歳で早世したことが大きかったかもしれない。
高杉はいうなればトリックスターである。
自分の追い求めるものが形をつくり完成に近づくと、その地位や責任を投げ出して違うものに走っていく。
花柳街で遊び、三味線で都都逸を唄い、詩に明るく、教養もある。
彼の生き方というものに、ある美学を感じるのは私だけだろうか。
高杉晋作は29歳で結核で亡くなるのだが「おもしろきこともなき世をおもしろく」という辞世の句を残している。